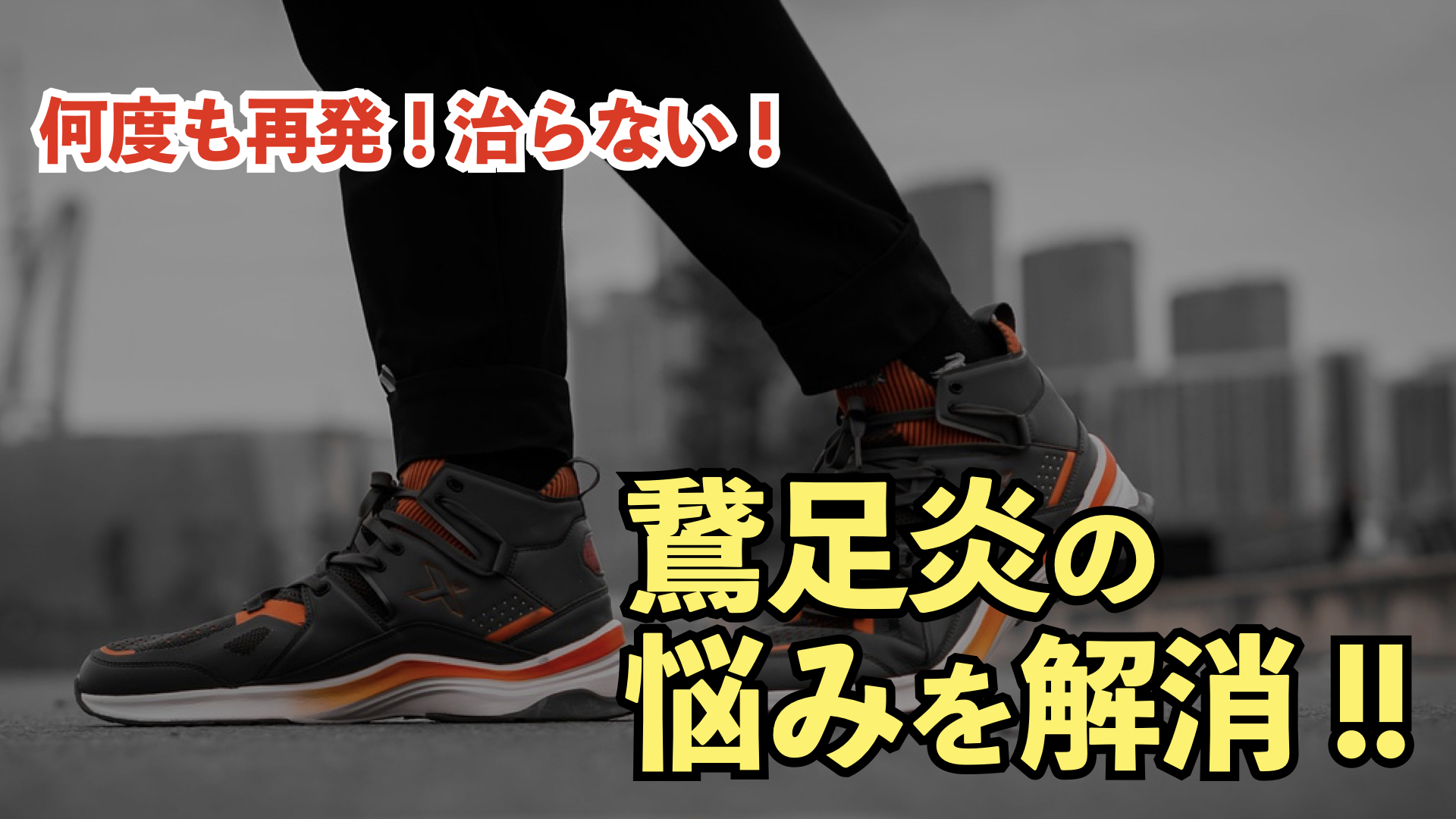鵞足炎は、マラソンやジョギング、サッカーや水泳など、スポーツをする人にとってはやっかいな存在だ。
完治したかと思えばまた痛くなる。
注射やテーピングで一時的に痛みが軽減しても、またいつ発症するかわからない。
数日で完治する人もいれば、再発を繰り返し、満足にトレーニングができないというアスリートや、痛くて歩けないという人もいる。
症状の深刻さは人それぞれだが、根本的な原因を解決しないことには再発する可能性が高い。
ここでは、鵞足炎の再発に悩んでいる人、いろいろな治療を試したが改善しない人に、鵞足炎を克服するための根本的な考え方と改善させる方法をご紹介します。
1. 鵞足炎(がそくえん)とは
膝の内側が痛くなり病院に行くと鵞足炎と診断されることがある。
聞きなれない言葉だが、鵞足とは、半腱様筋(はんけんようきん)、薄筋(はっきん)、縫工筋腱(ほうこうきん)の3つの筋肉の腱(筋肉の付け根)が集まっている部分の呼び名である。
この3つの筋肉は、骨盤から始まり、股関節と膝関節をまたぎ、最終的にスネの骨(脛骨 けいこつ)の上部内側、つまり、膝の下の内側に付着する。
この部分を鵞足と呼ぶ。
そして、この鵞足部分の炎症を鵞足炎という。
2. 鵞足炎の症状
鵞足炎の症状は、膝関節を動かしたり、押すと膝下内側に痛みがあり、腫れを伴うこともある。
はじめは、運動中や運動後に痛みを感じていたものが、進行すると歩行や階段の昇り降りでも痛みを感じるようになる。
重度になると、じっとしていても痛い状態が続く。
通常は数日から数週間で回復するが、再発、慢性化しやすいため、注意が必要だ。
また、膝の内側が痛いからといって全てが鵞足炎とは限らない。
疲労骨折などの可能性もあるので自己判断せずに病院で医師の診断を受けることが大切だ。
3. 鵞足炎の原因
鵞足炎は、一般的に鵞足を構成する筋肉(半腱様筋、薄筋、縫工筋)の使い過ぎが原因と言われ、膝関節の屈伸をくり返すことにより、膝内側側副靱帯と鵞足が何度も擦れ合い鵞足や鵞足滑液包に炎症をおこすとされている。
3-1. 鵞足炎とスポーツ
鵞足炎になりやすい代表的なスポーツは、サッカーやマラソン、水泳などがあり、最近では、登山や自転車などで鵞足炎になるケースも多い。
鵞足を構成する筋肉は太ももの裏側(半腱様筋)、前面(薄筋)、内側(縫工筋)というように、それぞれ異なる場所を経由して鵞足を形成する。
言い換えれば、大腿部(太もも)の筋肉に過剰な負荷をかけた結果、その付け根の鵞足が炎症をおこすということだ。
負荷には、継続的なものと、瞬間的なものがあり、その人の許容範囲を超えた場合に痛みや腫れとなって現れる。
マラソンは継続的に負荷がかかるスポーツであり、サッカーは瞬間的に過度の負荷がかかりやすいスポーツといえる。
3-2. X脚が原因の鵞足炎
X脚と呼ばれる外反膝は鵞足炎や鵞足滑液包炎になりやすいという研究がある。
症例対照研究:鵞足腱/滑液包炎症候群の危険因子
症例と対照の間で糖尿病、変形性膝関節症、肥満、膝の不安定性、内反膝変形(O脚)、および後足の不整配列の有病率に差はない。外反膝の変形(X脚)は鵞足腱炎/滑液包炎の危険因子であると思われる。
J Clin Rheumatol. 2007 Apr;13(2):63-
X脚とは、両足をそろえて真っ直ぐ立った時に、膝はくっつくが膝から下が外側に広がってくっつかない状態のことだ。
この場合、鵞足を構成する腱や筋肉は常に引っ張られていることになり、常にストレスがかかっている状態になる。
つまり、継続的に負荷をかけていることになる。
X脚だという人は少ないかもしれないが、膝を内側に寄せた状態、つまり、X脚の状態(膝が内側に入った状態)で鵞足に負荷をかけることはスポーツに限らず、日常生活でも多いのではないだろうか?
そして、X脚以外の要因である
- 変形性膝関節症
- 膝の不安定性
- O脚
- 足のアライメント不良
などに有病率の差がなかったということにも注目したい。
4. 鵞足炎の治療方法
鵞足炎の治療法には、保存療法と薬物療法があるが、ここでは保存療法について詳しく説明しよう。
ちなみに薬物療法とは、痛み止めの注射(ステロイドの局所注入)のことだ。
4−1. アイシングと安静
鵞足炎の症状として、痛みと腫れがある。
この時、痛みの治療と腫れの治療を分けて考える必要がある。
アイシングをする、安静にするというのは腫れや熱を抑えるためのものだ。
アイシングや安静によって一時的に痛みは軽減するが、痛みの治療ではないので、また過度の負荷がかかれば再発する可能性が高い。
炎症をおこして腫れや熱がある時には、まず腫れや熱をとることに専念すること。
痛みをとる治療はそれからだ。
4−2. テーピングとサポーター
痛みが酷くて日常生活に支障がでる場合は、テーピングやサポーターなどを使用して鵞足への負担を軽減する。
テーピングやサポーターにはいろいろな種類があり、それぞれの特徴を考えて使用すれば効果的だが、ここでは患部の保護という意味で使用する。
鵞足炎に限らず、歩行や階段の昇り降りなど、日常生活に支障がでるほどの痛みは、必要以上に安静にしたり、行動を制限してしまう。
リハビリを経験した方はおわかりのように、体は動かさないと動かなくなっていく。
テーピングやサポーターは、痛みが軽減するのであれば、最低限体を動かすためのサポートと考えて使用してほしい。
長期の使用は逆に動きを制限してしまう可能性があるので、おすすめしない。
5. 鵞足炎を改善するストレッチと筋トレ
腫れや熱が治まってきたら、痛みをとる、再発しない体をつくるといった治療が必要になる。
鵞足炎の痛みを改善するには、半腱様筋、薄筋、縫工筋の緊張を解かなければならない。
また、再発や慢性化を防ぐには、筋肉の緊張を持続させないことがポイントになる。
ここでいう筋肉の緊張とは、筋肉が硬くなっている状態、収縮している状態のことだ。
力が抜けずに、無意識に力が入っている状態ともいえる。
5−1. 鵞足炎を改善するためのストレッチ
筋肉の柔軟性を高めれば痛みがなくなる訳ではない。
緊張して縮んでいるものを無理に伸ばそうとしても傷めたり、逆に収縮してしまう。
このストレッチの目的は、ゆっくり動かす(伸縮させる)ことによって硬くなっている筋肉の緊張を緩めてあげることだ。
ストレッチは、股関節、太もも、ふくらはぎ、足首を中心に行なう。
いきなり膝から始めるより、鵞足部の周りから丁寧に緩めていく。
この時、足や股関節で、伸ばして痛いところを重点的に緩めていこう。
ポイントは、100%伸ばさないこと。MAXの70〜80%くらいまで伸ばしたら、そのままの状態で1〜2分ほどキープする。
ゆっくり呼吸をして力が抜けていくのを感じる。
これを数回くり返す。はじめのうちは、うまく脱力できないので、イメージするだけでもいい。
痛くない方の膝の感覚を参考にするとわかりやすい。
5−2. 鵞足炎を改善するための筋トレ
痛みと筋力は関係がない。
特にスポーツ障害のケースでは、通常の人より筋力がある人の方が圧倒的に多いはずだ。
ここで紹介する筋トレは、筋肉を鍛えるというものではない。
あくまでも筋肉を緩めることが目的の筋トレだ。
筋力を維持しながら改善しなければいけないアスリートの方は参考にしていただきたい。
基本的には、ストレッチと同じように、股関節、太もも、ふくらはぎ、足首を中心にメニューをつくる。
鵞足が痛いからといって鵞足だけにフォーカスするよりは、腰から下すべてを一つのまとまりと考えてメニューを作った方がいい。
スクワットを例に説明しよう。
まず注意していただきたいのが、痛いのを我慢して行わないことだ。
膝を曲げる角度や負荷は物足りないくらいでいい。
通常よりもゆっくり負荷をかけていき、力の入る場所、力の入っている感覚を感じながら行なう。
負荷をかけた状態で数秒キープして、スッと負荷を抜く。
この負荷を抜いた状態を数秒キープする。この時、力が抜けた感覚を味わうことが一番のポイントになる。
通常の筋トレが力を入れるトレーニングだとしたら、これは、力を抜くトレーニングだと思ってほしい。
力を入れる、力を抜くという動作を反復しているうちに、収縮していた筋肉は緩みだす。
何度か繰り返すうちに、痛みだす角度や痛くなる場所が変わってくる。
変わらない場合は、負荷を抜いた状態の時に深呼吸をして全身の筋肉をリラックスさせるといい。
以上のことを正しく理解して筋トレをすれば、同じトレーニングでも効果は全く違うものになるだろう。
筋力を鍛えることを目的に筋トレをするのではなく、筋肉の緊張を緩めることを目的にし、結果として筋力アップを狙う。
6. 鵞足炎の再発を予防する方法
鵞足炎になる原因の一つはオーバーユースだが、いくらハードなトレーニングをしても鵞足炎にならない人もいる。
これは、鵞足炎になる人は、鵞足炎になりやすい筋肉の状態で筋肉に負荷をかけるからだ。
鵞足炎を再発させないためには、再発する前に筋肉の状態に気づくことができるかできないかにかかっている。
前述したストレッチや筋トレは、予防法としても利用することができる。
力が思うように抜けない、スムーズに動かないといった異常をチェックするために活用してほしい。
「力を抜く」トレーニングをしてきたあなたは、今までよりも不調に早く気づき、早くケアすることができるはずだ。
7. 鵞足炎のまとめ
- 膝の内側に痛みを感じたら、自己判断せずに、専門医に診断してもらう。
- 患部に腫れや熱がある時は、炎症を抑えることに専念する。
- 痛みが強い場合は、テーピングやサポーターを使用して日常の活動を続ける。筋肉は動かないと動かなくなる。
- 腫れや熱が治ったら、ストレッチや筋トレなどで筋肉の緊張を緩めてあげる。筋肉を伸ばす、鍛えるを目的にしない。
- 自分のオリジナルメニューを作って自分の筋肉の状態をチェックする習慣をつける。早く異常に気づくことが最大の予防法。
今回は鵞足炎についてお伝えしたが、筋骨格系の痛みに共通する考え方として覚えてほしい。
ストレッチ、筋トレ、マッサージ等いろいろあるが、テクニックや方法が違っていても、根本的な考え方が合っていれば痛みは改善する。
痛みを感じたら、無意識に力が入っていないかをチェックして、「意識的に力を抜く!」ということを忘れないでほしい。